こんにちは、腹筋がカニの裏の人(プロフィールはこちら)です。
私は本記事を書いている時点(2025年10月)で40歳になりましたが、おそらく私と同年代やそれ以上の読者の方々で、若い頃に比べ疲れが取りにくくなったと感じている人は多いのではないでしょうか?
実際に、30代以降ではミトコンドリア機能、酸化ストレス耐性、ホルモン・神経系・睡眠などに年齢変化が現れ、回復力やパフォーマンスに影響が出やすくなります。
そこで、今回は30代以降の方に特にお勧めしたい、疲労回復に役立つサプリメントを8つ紹介したいと思います。
※本記事で紹介しているサプリメントは、筆者が実際に使用しているものを含め、できる限り安全性の高いメーカーを選んでいます。
ただし、すべてがアンチドーピング認証を受けているわけではありませんので、競技者の方は購入・使用の際に各自で成分や製造元をご確認のうえ、自己責任で判断してください。
なぜ30代から回復力が落ちるのか
30代に差しかかると、トレーニングの疲労が翌日に残りやすくなったり、睡眠を取っても疲れが抜けない感覚を覚える方も多いと思います。これは単なる“気のせい”ではなく、体内の代謝・ホルモン・神経の働きに明確な変化が起きているためです。
- ① ミトコンドリア機能の低下:ATP(エネルギー)生産効率が落ち、筋疲労の回復が遅くなる。
- ② 抗酸化力の低下:活性酸素を除去する酵素の働きが衰え、細胞のダメージ修復に時間がかかる。
- ③ ホルモン分泌の減少:テストステロンや成長ホルモンの分泌量が20〜30代を境に減少する。
- ④ 神経・睡眠バランスの乱れ:ストレスホルモン(コルチゾール)が優位になり、深い睡眠が取りにくくなる。
こうした複合的な変化に対して、食事やトレーニングだけで補うのは難しくなってきます。そこで役立つのが、各機能をピンポイントで支える以下のサプリメントです。
コエンザイムQ10
まず1つ目は「コエンザイムQ10」です。
あまり聞き馴染みが無いかもしれませんが、このコエンザイムQ10は疲労回復やトレーニングパフォーマンスに大きな影響を与える栄養素です。
体内でも生成されますが、30歳から生成量が減少すると言われているため、体外からの摂取が必要になってきます。
このコエンザイムQ10の主な働きには、以下のようなものがあります。
抗酸化作用
日頃から激しい筋トレを行っているトレーニーは、体内の活性酸素量が高い傾向にあります。
この活性酸素は体内の正常な細胞を傷つけ疲労回復を阻害してしまうのですが、この活性酸素を取り除く力(酸化効力)は30歳以降から低下していきます。
コエンザイムQ10には、その活性酸素を取り除く抗酸化作用があり、積極的に摂取していきたい栄養素になります。
エネルギー生産
コエンザイムQ10は主にミトコンドリア内に存在し、体内に摂取した糖質からATPを生成する過程(電子伝達系)において不可欠の栄養素です。
ATPはウエイトトレーニングを行う際の主なエネルギー源となるため、年齢によるコエンザイムQ10の減少(つまりATPの生産量の低下)は、トレーニングパフォーマンスの低下に直結します。
これを防ぐ目的においても、コエンザイムQ10を外部から摂取することが大切です。
肝機能向上
コエンザイムQ10には肝機能を向上させる役割があると言われています。
日頃、高タンパクな食事を取っているトレーニーは肝臓に負担がかかりやすいため、この肝機能向上効果はトレーニーにとって嬉しいメリットと言えるでしょう。
コエンザイムQ10は食品からも摂取することはできますが、1日の必要量を摂取しようとした場合、最も多く含まれるイワシでさえ毎日約26匹(1匹60gとして換算)も食べなくてはならないため、サプリメントからの摂取を推奨します。
また、コエンザイムQ10は脂溶性であるため、全卵やサーモンなど、なるべく脂質の多い食品と一緒に摂るようにしましょう。
体感で期待できる効果
コエンザイムQ10を摂取すると、以下のような体感が期待できます。
- トレーニング中バテにくくなる(エネルギー切れが減る)
- 高重量のトレーニングをしても最後まで粘れる感覚が出る
- 朝の目覚めが軽くなり、疲労の抜けが早く感じられる
- 減量期の倦怠感が軽くなる
- 減量期の“力が出にくい”感覚が起きにくくなる
- 階段の上り下りや通勤時など、日常動作でも体が軽く感じられる
また、持久系競技者では「運動後の心拍回復スピードの改善」や「筋肉中の乳酸蓄積の低下」が報告されており、トレーニング後の回復効率を高める栄養素としても注目されています。
私自身の体感としても、CoQ10を毎朝摂取しているのですが、1日の活動が軽く感じられるようになり、「疲れにくい」というより“エネルギーが途切れない”という印象を受けました。
このように、コエンザイムQ10は単に「疲れを取るサプリ」ではなく、筋肉・心臓・脳のエネルギー代謝を底上げする総合的な“活力サポート成分”として機能します。
アンチドーピングの観点でネイチャーメイド製は安心して選びやすいブランド・製品になりますので、コエンザイムQ10を摂取するのであればこちらがお勧めです。
アスタキサンチン
2つ目は「アスタキサンチン」です。
アスタキサンチンは、サーモンやエビ、イクラなどに含まれる赤橙色の天然色素(カロテノイド)で、非常に強力な抗酸化作用を持っています。
先ほど紹介したコエンザイムQ10よりも高い抗酸化力を持ち、その強さは約600倍に達すると言われています。
筋トレや有酸素運動を行うと、体内では大量の活性酸素が発生します。活性酸素は筋細胞を傷つけ、炎症や疲労の原因となりますが、アスタキサンチンはその活性酸素を効率よく除去してくれます。
強力な抗酸化作用
アスタキサンチンの最大の特徴は「強力な抗酸化作用」です。
通常、抗酸化物質は脂溶性か水溶性のどちらかに偏るため、細胞膜の片側しか守れません。
しかしアスタキサンチンは、脂質二重膜の両面に安定して結合し、細胞膜の「内側」と「外側」の両方をまたいで存在できるため、細胞の内外から活性酸素を中和することができます。
そのため、トレーニング中に発生する酸化ストレスから筋肉細胞を保護し、結果的に筋損傷の軽減・疲労回復の促進につながります。
抗炎症・血流改善作用
アスタキサンチンには、炎症を引き起こすサイトカイン(IL-6やTNF-αなど)の発現を抑える働きも確認されています。
また、血液中の赤血球膜の柔軟性を高め、血流を改善する作用もあるため、トレーニング中の酸素運搬効率を高めることにもつながります。
推奨摂取量とタイミング
摂取量の目安は1日あたり4〜12mg程度です。疲労感が強い方や減量期などストレスの高い時期は、上限の10〜12mgを目安にすると良いでしょう。
また、アスタキサンチンは脂溶性のため、脂質を含む食事中に摂取することで吸収率が高まります。コエンザイムQ10やオメガ3脂肪酸と一緒に摂るのもおすすめです。
体感で期待できる効果
トレーニング翌日の疲労感や筋肉痛の軽減、肌ツヤの改善、目の疲れの軽減などが期待できます。
また、減量末期や有酸素運動量が増える時期にアスタキサンチンを取り入れると、全身のコンディションが安定しやすく、パフォーマンス低下の予防にも役立ちます。
自分はDHCのアスタキサンチンを愛用しています。
これを摂取し始めてから、明らかに日頃の疲労感が軽減されたことを体感しているので、個人的には皆さんに”強く”お勧めしたい商品です。
α-リポ酸(ALA)
3つ目は「α-リポ酸(アルファリポ酸)」です。
α-リポ酸は、体内で「糖や脂質をエネルギーに変える」際に必要な補酵素として働く成分です。ビタミン様物質とも呼ばれ、栄養素の代謝効率を高める働きを持っています。
私たちが摂取した炭水化物(グルコース)は、最終的にミトコンドリア内で燃やされ、ATP(エネルギー)に変換されます。この“燃やす工程”の要となるのが、α-リポ酸です。
エネルギー代謝を支える補酵素
α-リポ酸は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体(TCA回路への入口)に関与し、糖質から生じたピルビン酸をアセチルCoAに変換する際の補助因子として働きます。
この反応がスムーズに行われることで、ミトコンドリアでのATP(エネルギー)生産効率が高まり、トレーニング中のエネルギー切れを防ぎます。
つまり、α-リポ酸は「糖質をしっかり燃やしてトレーニングのエネルギーに変える」ための触媒のような役割を担っているのです。
抗酸化作用と再生作用
α-リポ酸は、他の抗酸化物質(ビタミンCやE、グルタチオンなど)を「再生」する力を持つことでも知られています。
トレーニングやストレスによって体内に増えた活性酸素を中和するだけでなく、使い終わった抗酸化物質を再び有効な形に戻して再利用するため、「抗酸化ネットワークの司令塔」とも言われます。
インスリン感受性の改善
α-リポ酸には、インスリンの働きをサポートする効果も報告されています。筋細胞へのブドウ糖の取り込みを促進し、血糖値の安定化を助けます。
これにより、トレーニング後のグリコーゲン補充がスムーズになり、次のトレーニングに向けた回復力も高まります。
推奨摂取量とタイミング
一般的な摂取目安は、1日あたり300〜600mg程度です。より生体利用率の高い「R-ALA(R体)」を使用する場合は、100〜300mgで十分とされています。
摂取タイミングは食後またはトレーニング後が理想的です。炭水化物を摂取するタイミングに合わせると、糖代謝をより効率的にサポートできます。
体感で期待できる効果
- トレーニング後の疲労感が軽減される
- 減量期でも集中力が維持しやすく、エネルギー切れしにくい
- 血糖の安定化によって、食後の眠気やだるさを感じにくくなる
また、α-リポ酸はコエンザイムQ10と併用することで、ミトコンドリアのエネルギー産生をより強力にサポートするので、併せて摂取すると良いでしょう。
自分は現在は摂取していませんが、過去にネイチャーメイド製のαリポ酸を愛用していました。
コエンザイムQ10でも触れましたが、ネイチャーメイド製はアンチドーピングの観点からも安心して選びやすいブランド・製品になりますので、αリポ酸を摂取したいのであればこちらをお勧めします。
ZMA(亜鉛+マグネシウム+ビタミンB6)
4つ目は「ZMA」です。ZMAとは、亜鉛(Zinc)、マグネシウム(Magnesium)、ビタミンB6を組み合わせたサプリメントで、特に回復力・睡眠の質・ホルモンバランスをサポートする目的でトレーニーに広く使われています。
この3つの栄養素はそれぞれ単体でも重要ですが、組み合わせて摂ることで相乗的に作用し、身体の修復力を高めます。
亜鉛(Zinc)
亜鉛はタンパク質合成・テストステロン分泌・免疫機能に深く関わるミネラルです。筋肉の修復や成長を促すうえで欠かせない栄養素であり、トレーニングによる発汗や高タンパク食によって失われやすい特徴があります。
また、亜鉛は脳下垂体のホルモン分泌にも関与しており、男性ホルモン(テストステロン)や成長ホルモンの分泌をサポートする働きもあります。
マグネシウム(Magnesium)
マグネシウムは筋肉の収縮と弛緩、神経の伝達、エネルギー代謝を支える重要なミネラルです。欠乏すると筋肉がつりやすくなったり、寝つきが悪くなるなどの不調が起こりやすくなります。
特に、マグネシウムは副交感神経を優位にする働きを持ち、就寝前に摂取することでリラックスを促し、睡眠の質を高めてくれます。
ビタミンB6
ビタミンB6は、アミノ酸を筋肉合成に使うための「変換酵素」をサポートするビタミンで、亜鉛やマグネシウムと同時に働くことで、タンパク質の代謝をスムーズにします。
また、神経伝達物質セロトニンの生成にも関与するため、心の安定や睡眠リズムの改善にも関わります。
ZMAとしての相乗効果
これら3つを組み合わせることで、単体摂取時よりも吸収効率と生理的効果が高まるとされています。ZMAの特徴的なメリットは次の3点です。
- 睡眠の質の向上
- トレーニング後の筋肉修復の促進
- テストステロン分泌のサポート
特にハードトレーニング期や減量期など、回復が追いつかない時期に導入すると効果を実感しやすいです。
推奨摂取量とタイミング
1日あたりの目安は以下の通りです:
- 亜鉛:20〜30mg
- マグネシウム:400〜450mg
- ビタミンB6:10〜20mg
ZMAは空腹時、特に就寝30〜60分前に摂るのがベストです。
また、カルシウムは亜鉛の吸収を妨げるため一緒に摂るのは避けましょう。
体感で期待できる効果
- 翌朝の目覚めがスッキリし、疲労が抜けやすくなる
- トレーニング後の筋肉の張りやこわばりが軽減する
- 睡眠が深くなり、夜中に目が覚めにくくなる
- 減量期でも集中力が維持しやすくなる
- ホルモンバランスが整い、やる気・活力が出やすくなる
ZMAは直接的に筋肉を大きくするサプリではありませんが、「トレーニングの質を底上げするベースサプリ」として非常に優秀です。
特に30代以降のトレーニーにとっては、睡眠・回復・ホルモンの維持が成長のカギを握るため、ZMAを導入する価値は十分にあると思います。
ZMAに関してはKentaiの商品が最も安心して使用できると思います。
グルタミンも配合されており、回復をサポートする目的に合った商品です。
ホスファチジルセリン(PS)
5つ目は「ホスファチジルセリン(PS)」です。ホスファチジルセリンは大豆や卵黄などに含まれるリン脂質の一種で、特に脳や神経細胞の膜構成成分として重要な役割を担っています。
一般的には「集中力や記憶力を高めるサプリ」として知られていますが、トレーニーにとってはストレスホルモン(コルチゾール)の抑制という観点で非常に有用な成分です。
コルチゾール抑制効果
ホスファチジルセリンは、副腎皮質から分泌されるストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を抑制する作用があります。
コルチゾールは、トレーニング後の回復や筋肥大を妨げる要因の一つであり、過剰に分泌されると筋タンパク分解を促進し、免疫力低下や睡眠の質の悪化を引き起こします。
PSを摂取することでこのコルチゾールの過剰分泌が抑えられ、トレーニングによるストレスからの回復がスムーズになります。
脳疲労・集中力の改善
ホスファチジルセリンは神経細胞膜の柔軟性を保ち、神経伝達物質(アセチルコリンやドーパミンなど)の働きをサポートします。
これにより、集中力・判断力・反応速度が向上し、長時間のトレーニングや仕事中の“脳の疲れ”を軽減します。
睡眠と回復への影響
PSによってコルチゾール分泌が抑制されることで、夜間の副交感神経優位状態が保たれやすくなります。これにより、眠りが深くなり、翌日の疲労回復が早まります。
特に、減量末期や大会直前などストレスが高まりやすい時期に導入すると、睡眠の質を守りながらコンディションを安定させる効果が期待できます。
推奨摂取量とタイミング
摂取量の目安は1日あたり100〜300mg程度です。減量期などには、やや多めの200〜300mgが推奨されます。
摂取タイミングは、就寝前またはトレーニング後が理想的です。夜に摂ることでリラックス効果が高まり、睡眠中のコルチゾール分泌を抑えやすくなります。
体感で期待できる効果
- 睡眠の質が上がり、朝の目覚めが軽くなる
- トレーニングでの集中力が持続しやすくなる
- 減量期のキレ食いを防いだり、イライラしにくくなる
- メンタルの安定感が増し、日中のパフォーマンスが向上する
PSは「筋肉を増やす」サプリではありませんが、メンタルとホルモンのバランスを整えてトレーニングの質を底上げする点で、特に30〜40代以降のトレーニーに強くお勧めできる成分です。
ホスファチジルセリンを扱うメーカーを調べたところ、DHCのものが最も安心して利用できそうです。
ビタミンB群
6つ目は「ビタミンB群」です。ビタミンB群は、エネルギー代謝や神経機能、ホルモンバランスなどに関わる“縁の下の力持ち”のような栄養素で、特にトレーニーにとっては欠かせない基礎サプリの一つです。
ビタミンB群は8種類のビタミンで構成され、それぞれが異なる役割を持ちながらも互いに補い合って働きます。そのため、単体よりも「ビタミンB群」としてまとめて摂取するのが理想的です。
エネルギー代謝を支える(B1・B2・B3・B5)
ビタミンB1は糖質を、B2とB3は脂質を、B5(パントテン酸)は脂肪酸やコレステロールの代謝をサポートします。これらは体内のミトコンドリアでATP(エネルギー)を生み出す際に必須の補酵素として働きます。
つまり、ビタミンB群が不足していると、どれだけ炭水化物やタンパク質を摂ってもエネルギーに変換できず、「疲れが抜けない」「力が入らない」といった状態に陥りやすくなります。
筋肉合成と神経伝達(B6・B12・葉酸)
ビタミンB6はアミノ酸代謝を助け、摂取したタンパク質を効率よく筋肉合成に使えるようにします。また、神経伝達物質の合成にも関与し、トレーニング中の集中力の維持にも役立ちます。
B12と葉酸は赤血球の生成に関わり、酸素運搬能力を高めることで持久力アップや疲労回復の促進に貢献します。これらが不足すると、貧血気味になったりトレーニングパフォーマンスが落ちやすくなります。
ストレス耐性とホルモンバランス(B5・B6・B12)
ビタミンB群は、副腎皮質ホルモン(コルチゾールなど)の分泌バランスを整える働きもあります。特にB5(パントテン酸)は“抗ストレスビタミン”とも呼ばれ、ホルモン分泌や神経安定に欠かせません。
過度なトレーニングや睡眠不足、減量期のストレスなどで副腎が疲弊すると、コルチゾール過剰やホルモンバランスの乱れが生じやすいため、ビタミンB群を意識的に補うことで心身の安定を維持できます。
推奨摂取量とタイミング
B群は水溶性で体内に蓄積されにくいため、1日2〜3回に分けて摂取するのが理想です。一般的な目安は以下の通りです:
- ビタミンB1:10〜30mg
- ビタミンB2:10〜30mg
- ビタミンB6:10〜30mg
- ビタミンB12:100〜500μg
- ナイアシン(B3):20〜50mg
- パントテン酸(B5):20〜50mg
- 葉酸:200〜400μg
摂取タイミングは朝食後やトレーニング前後が最適です。エネルギー代謝が活発になるタイミングで摂ることで、効果を最大化できます。
体感で期待できる効果
- トレーニング後の疲れやだるさが軽減される
- トレーニング中の集中力やモチベーションが維持しやすくなる
- 減量期でもエネルギー切れしにくくなる
- イライラしにくくなり、メンタルの安定を実感する
ビタミンB群は直接筋肉を増やすサプリではなく、“栄養の燃焼効率を上げるブースター”のような存在です。トレーニング量が増えるほど需要も高まるため、食事だけに頼らずサプリで補うと良いでしょう。
ビタミンB群についてもネイチャーメイドの商品がありました。
ただ、自分はビタミンB群の補給としてKentaiのマルチビタミン・ミネラルを愛用していますので、こちらも併せて紹介しておきます。
ビタミンB群以外にも、トレーニーに必要なビタミン・ミネラルがバランス良く配合されている商品です。
オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)
7つ目は「オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)」です。オメガ3は青魚や亜麻仁油などに含まれる脂質で、抗炎症作用・血流改善・ホルモンバランスの安定など、トレーニーにとって欠かせない多面的な効果を持つ栄養素です。
特にEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)は、細胞膜を柔軟に保ち、体内の炎症反応をコントロールする働きを持ちます。日常的に摂取することで、筋肉・関節・脳・心血管など、全身のパフォーマンスを支えます。
炎症の抑制と筋肉の回復促進
トレーニング後、筋肉に微細な損傷が起きると体内では炎症反応が起こります。これは修復のために必要な反応ですが、過剰になると回復が遅れ、慢性的な疲労や関節痛の原因になります。
EPAは、この炎症反応を引き起こす物質(プロスタグランジンE2やロイコトリエンB4など)の生成を抑え、筋肉や関節の炎症を穏やかに抑制します。その結果、トレーニング後の筋肉痛や関節の違和感が軽減され、回復が早まります。
血流促進と栄養輸送の効率化
オメガ3は血液中の赤血球膜を柔らかくし、血液の粘度を下げることで血流を改善します。これにより、筋肉への酸素供給や栄養輸送がスムーズになり、疲労物質の排出も効率化します。
特に減量期では血流が悪くなりやすいため、EPAやDHAを補うことで代謝が落ちにくく、トレーニング後のパンプ感も維持しやすくなります。
ホルモンバランスとメンタルの安定
オメガ3脂肪酸は、脳神経の細胞膜にも豊富に存在し、神経伝達物質の働きを安定させます。特にDHAは脳の構成脂質の約30%を占め、集中力・判断力・メンタルの安定に関与します。
また、EPAは副腎のホルモン生成をサポートし、ストレスホルモンの過剰分泌を抑える働きがあるため、ZMAやホスファチジルセリンと組み合わせることで心身両面のリカバリーを強化できます。
脂肪燃焼の促進
EPAとDHAは、細胞膜内の代謝スイッチ(PPARα・AMPK)を刺激し、脂肪の酸化(燃焼)を促進します。これにより、体脂肪を効率よくエネルギーに変換できるようになり、減量期の停滞を防ぐ助けになります。
また、オメガ3を摂ることでインスリン感受性も改善され、糖質を摂っても脂肪として蓄積しにくくなるというメリットもあります。
推奨摂取量とタイミング
1日あたりの目安はEPA+DHAで1000〜2000mg程度です。トレーニングを行っている場合や脂質の少ない減量食を続けている方は、やや多めの摂取が推奨されます。
摂取タイミングは食後が推奨され、特に脂質を含む食事(卵・サーモン・アボカドなど)と一緒に摂ることで吸収率が高まります。
体感で期待できる効果
- 関節の違和感や炎症の軽減
- トレーニング後の疲労感の軽減、回復の促進
- 脂肪燃焼
- 集中力の維持、メンタルの安定
オメガ3は「炎症を抑え、血を流し、心を整える」万能サポート栄養素です。CoQ10やアスタキサンチンと併用すれば、細胞レベルでの抗酸化・抗炎症ネットワークが完成します。
私はマイプロテインのオメガ3脂肪酸を普段から愛用しています。
クレアチン
8つ目は「クレアチン」です。
クレアチンは年齢に関係なく摂取しているトレーニーが多いのではないでしょうか?
クレアチンは、筋肉内で瞬発的なエネルギー(ATP)を再合成するための補助物質であり、トレーニングパフォーマンスを底上げする最も実証データの多いサプリメントの一つです。
自然界では赤身肉や魚に含まれますが、食品から十分な量を摂ることは難しく、サプリメントとしての補給が最も効果的です。
エネルギー再合成(ATP-PC系)のサポート
筋肉が収縮する際の直接的なエネルギー源はATP(アデノシン三リン酸)ですが、このATPは数秒で枯渇してしまいます。そこで活躍するのがクレアチンです。
クレアチンは筋内で「クレアチンリン酸(PCr)」として貯蔵され、ATPが分解された際にリン酸を再供給することで、再びATPを再合成します。つまり、クレアチンは短時間・高強度の運動を“もう一段階長く”続けられるエネルギー供給源になります。
筋力・筋量アップ
クレアチン補給によって筋細胞内の水分量(細胞内水分=筋細胞ボリューム)が増加し、筋合成に関わるmTOR経路が刺激されます。この反応により、筋肉の合成反応が高まり、トレーニング効果が出やすくなります。
また、エネルギー供給効率が上がるため、トレーニング中の出力(重量・レップ数)を維持しやすく、結果的に筋肥大を促進します。
脳と神経系への好影響
クレアチンは筋肉だけでなく、脳にも存在しており、神経細胞のエネルギー供給をサポートします。近年の研究では、集中力・判断力・ストレス耐性の改善といった認知機能への好影響も報告されています。
特に睡眠不足や減量中などエネルギー不足の状態では、クレアチンがその効果を発揮しやすいといえます。
推奨摂取量とタイミング
クレアチンの一般的な摂取量は1日3〜5gです。ローディング(初期の貯蔵期間)として最初の5〜7日間だけ1日20g(4回に分けて)摂取する方法もありますが、近年では毎日3〜5gを継続する方法でも十分に筋肉内に蓄積されるとされています。
摂取タイミングは、トレーニング後(糖質+プロテインと一緒に摂る)が最も効果的です。これはクレアチンの筋細胞への取り込みがインスリン分泌によって促進されるためです。
体感で期待できる効果
- 高重量トレーニングのパフォーマンスの安定
- 最後の1~2レップを出し切ることができる
- トレーニング後の回復スピードの向上
- 減量期の出力低下の抑制
クレアチンは「筋肉を動かすエンジンオイル」のような存在であり、最も研究された信頼性の高いサプリメントの一つです。特に30代以降のトレーニーでは、筋力・回復力の維持に役立ちます。
また、これまで紹介してきたCoQ10・αリポ酸・オメガ3などと併用することで、エネルギー代謝系+抗酸化系の両輪が揃い、トレーニング効率を最大化できます。
クレアチンはゴールドジム製のものがオススメです。
価格は他メーカーに比べると高いですが、クレアチンのように少量で効果を発揮してくれるサプリメントは、ゴールドジム製など高品質なものを選択することをお勧めします。
まとめ
ここまで紹介してきた8つのサプリメントは、単体でも効果的ですが、組み合わせることで疲労・代謝・ホルモン・メンタルといった4つの軸を総合的にサポートすることができます。
| サプリ名 | 主な効果 | 摂取タイミング |
|---|---|---|
| コエンザイムQ10 | 疲労回復/抗酸化/エネルギー生産/肝機能サポート | 朝・昼(脂質と一緒に摂ると◎) |
| アスタキサンチン | 強力な抗酸化/筋損傷軽減/炎症抑制 | 食後(脂質と一緒に摂ると◎) |
| α-リポ酸(ALA) | 糖代謝促進/抗酸化物質の再生/血糖コントロール/疲労軽減 | 食後またはトレ後 |
| ZMA(亜鉛+マグネシウム+B6) | 睡眠の質向上/テストステロン維持/筋修復促進/回復力強化 | 就寝30〜60分前(空腹時) |
| ホスファチジルセリン(PS) | コルチゾール抑制/ストレス軽減/集中力・記憶力向上 | トレ後または就寝前 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝促進/神経機能維持/疲労軽減/ホルモン代謝補助 | 朝・昼・トレ前後 |
| オメガ3(EPA・DHA) | 炎症抑制/血流改善/脂肪燃焼促進/メンタル安定 | 朝食後・夕食後 |
| クレアチン | 出力維持/筋合成促進/瞬発力向上/回復スピード改善 | トレ後(糖質+プロテインと一緒に摂ると◎) |
これらを全て一度に取り入れるのは大変ですので、まずは、年齢に伴い自分が弱ってきていると感じる部分(疲労、睡眠、代謝、集中力、etc)を見極め、それを補えるようなサプリメントに対象を絞ってみるといいと思います。
👇こちらでは、年齢に関係なく筋肥大に役立つビタミン・ミネラル群を紹介していますので、併せて参考にしてみてください。
👇こちらでは私が実際に摂取しているサプリメントを紹介しているので、こちらも参考にどうぞ。
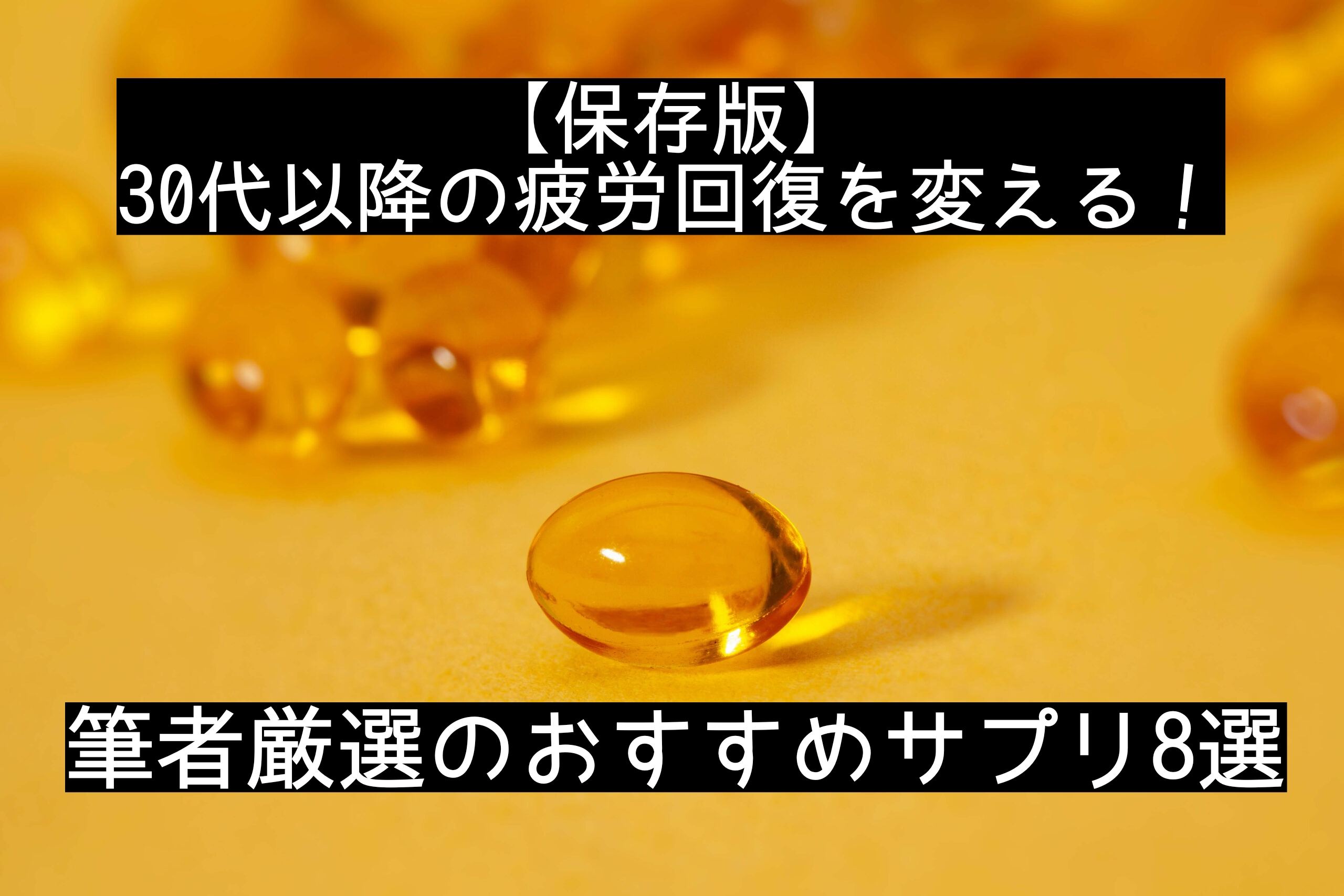




コメント