こんにちは、腹筋がカニの裏の人(プロフィールはこちら)です。
「最初はあんなにやる気があったのに、最近は少しモチベーションが落ちてきた…」
そんな経験は誰にでもありますよね。
筋トレでもダイエットでも、最初はやる気に満ちていても、時間が経つと少しずつモチベーションは下がっていってしまうもの。
やる気に波があるのは自然なことですが、大切なのは、モチベーションが下がっても行動を止めない工夫を持っているかどうかです。
この記事では、心理学的にも効果が認められているモチベーションを維持する為の6つの方法を紹介します。
どれも簡単に実践できる内容ですので、皆さんもよかったら試してみて下さい。
目標のハードルを下げる
「目標は大きい方がいい」「ストイックな人ほど偉い」――世間では一般的にそんなイメージを持っている人は多いと思います。
しかし実際には、目標が大きすぎるほどプレッシャーは大きくなり、途中で息切れしやすく、また、ストイックすぎるほど自分を追い込みすぎてしまうものです。
もし今の目標が辛く感じるのなら、まずはハードルを下げてみましょう。
例えば、「10kg減量する」という目標を立てていたとします。
しかし、いざ挑戦しようとしても、(特に初めて減量をする人にとって)その目標は高いものに感じてしまうことでしょう。ボディビルの大会に毎年出ているような選手であれば慣れたものですが、そうでない人にとって10kgのダイエットは非常に高いハードルに感じると思います。
そして、たとえ最初はやる気に満ち溢れていたとしても、だんだんとそのモチベーションは必ず下がっていってしまうものです。そこで大切になのが「いったん目の前の目標のハードルを下げてみる(実践しやすい目標に変えてみる)」ということ。
たとえば、「まずは毎日の白米の量を1食あたり30gだけ減らしてみよう」とか「仕事からの帰り道を少しだけ遠回りしてみよう」とか。そんな小さな一歩で十分なのです。
ハードルを下げることは”甘え”ではありません。
むしろ、現実的に続けられるモチベーションを維持することが、結果的に目標達成のための最短距離に繋がるのです。
小さな成功体験を積み重ねる
この「目標を小さくする」というのは、自信を身につける上でも大切になってきます。
例えば、先ほどの「10kg減量する」という目標に対して、思ったように体重が減らないと「自分はダメなやつだ」「もう無理かも」と自信を失ってしまいがち。
でも、目標を小さく設定しなおすことで、その目標を達成した時には「自分にもできた!」という”小さな成功体験”になり、自分に自信をつけてくれます。そしてその自信が、次の行動を生む原動力になるのです。
つまり、どんなに小さなことでも「できた自分は偉い」と認めてあげることが大切。
- 白米の量を30g減らすことができた
- 今日もジムに行けた
- 減量中でもトレーニング強度を保つことができた
- 昨日よりフォームが安定した
- 体重は減っていないけど、食事のコントロールはできた
- 新しいトレーニングを教えてもらった
- 新しい種目に挑戦できた
こうした“小さな達成”の積み重ねが、やがて大きな自信や結果を生み出してくれます。
つまり、小さな成功体験を見逃さず、自分を認めることがモチベーションを支える最大のコツなのです。
モデリングを実践する
モデリングとは、心理学者アルバート・バンデューラの「社会的学習理論」に基づいた考え方です。
簡単に言えば、「憧れの人物を観察し、その考え方や行動を取り入れることで自分の行動を変えていく」手法です。
たとえば、あなたが目標としているインフルエンサーや尊敬している選手がいるなら、「あの人ならこの場面でどう行動するだろう?」「どんなトレーニングをしているだろう?」と想像してみてください。
そして、自分もその人になりきってトレーニングをしてみると、不思議と集中力が高まり、メンタルも整っていきます。また、あたかも自分がその人になりきることで、モチベーションのアップや自信をつけることにも繋がっていきます。
これは単なる真似ではなく、理想の自分を先に“演じる”ことで、現実を引き寄せる心理的トレーニングです。

自分もたまに鈴木雅さんのトレーニングDVDを思い出し、雅さんになりきってトレーニングすることがあります笑
フューチャー・ペーシングを実践する
私が実践して最も効果を感じている方法のひとつに、”フューチャー・ペーシング(Future Pacing)“というものがあります。
これは「夢や目標を叶えた未来の自分の姿を想像する」というイメージトレーニングです。
夢や目標を叶えた瞬間(大会で優勝した瞬間や、理想の体型を手に入れた時)の自分を、具体的に頭の中でイメージします。
どんな場所にいて、どんな服を着て、どんな表情で、どんな感情を抱いているか。
その瞬間の「音」「匂い」「空気」などの臨場感も合わせて想像してみます。
そして、その夢や目標を叶えた未来の自分から、今の自分に向けてメッセージをもらうのです。
「今は焦らなくていいよ」「君の努力は必ず報われる」「君のおかげで目標が達成できたんだ」――そんな言葉を未来の自分から受け取ってみて下さい。
このワークを続けていくことで未来の自分が背中を押してくれるような感覚が得られ、高いモチベーションを維持することができるのです。
リフレーミング
リフレーミング(Reframing)という考え方も、心理学でよく使われる方法です。
これは、「出来事そのものを変えられなくても、意味づけを変えることで気持ちを立て直す」というもの。
たとえば――
- 「減量がつらい」→「それだけ本気で挑戦している証拠」
- 「体重が減らない」→「体が順応している途中だから焦る必要はない」
- 「今日は気分が乗らない」→「そんな日でもジムに来れた自分を褒めよう」
- 「負けた」→「成長の余地を見つけるチャンスをもらった」
このように「見方を変える」だけで、同じ出来事が全く違う意味を持つようになります。
リフレーミングは、心の柔軟性を高めるトレーニングです。
思い通りにならない時こそ、ポジティブな言葉で自分を励ましていきましょう。
ソーシャルサポート
モチベーションを保つうえで意外と見落とされがちなのが、人とのつながりです。
人は一人でできることには限界がありますが、周りに自分を支えてくれる存在がいるだけで前に進む力は何倍にもなります。
たとえば、ジムの仲間やトレーナー、家族や友人――。
誰かに「調子どう?」と声をかけてもらえたり、「頑張ってるね」と言われるだけで、心がふっと軽くなった経験はありませんか?
心理学ではこれをソーシャルサポート(Social Support)と呼び、研究でも「人とのつながりがストレス耐性やパフォーマンスの維持に大きく影響する」と証明されています。
特に減量期や大会前など、精神的にきつい時期こそ、周りに相談できる環境を持つことが大切です。
弱音を吐いたり、愚痴を言ったりしても構いません。
それを受け止めてくれる仲間がいるだけで、もう一度立ち上がる力が湧いてくるものです。
“あの人が頑張っているから自分も頑張れる“という感覚は、それだけで孤独を和らげ、自らに力を与えてくれます。
苦しい時に人に頼るのは悪いことではありません。支え合いながら続けていくことこそ、努力を継続するための最大の秘訣だと思います。
まとめ
大きな目標になればなるほどモチベーションを維持するのは大変ですが、そんな時は無理に維持しようとせず今回ご紹介した内容を試してみて下さい。
- 目標のハードルを下げる
- 小さな成功体験を積み重ねることで自信をつける
- モデリングで目標の人になりきる
- フューチャー・ペーシングで「目標を叶えた未来の自分」からメッセージをもらう
- リフレーミングで気持ちをプラスに変える
- ソーシャルサポートで人とのつながりを大切にする
これらを意識するだけで、最終目標のハードルも下がっていくはずです。途中で挫折しかけた時には皆さんもぜひ実践してみてください。
👇モチベーション維持の方法については以下の記事でも紹介していますので、よろしければこちらも参考にどうぞ


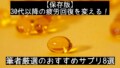

コメント