こんにちは、腹筋がカニの裏の人(プロフィールはこちら)です。
「筋トレを頑張っているのに、なかなか筋肉が成長しない…」そんな悩みを感じたことはありませんか? 多くのトレーニーは「休養=睡眠」と考えがちですが、それだけでは十分ではありません。
医学博士の片野秀樹氏(著書『休養学』)によると、休養には7つのタイプが存在し、それらをバランスよく取り入れることで、心身の疲労を根本から回復できるといいます。 今回は、この「休養学」の考え方を紹介し、筋トレ・筋肥大への応用方法を紹介してみたいと思います。
片野秀樹博士が提唱する“休養”の新常識
片野秀樹氏は、一般社団法人日本リカバリー協会の代表理事を務める医学博士で、2024年に出版された著書『休養学:あなたを疲れから救う』が16万部を超えるベストセラーとなっています。
この本の中で片野氏は、「疲労回復とは単に休むことではなく、“攻めの休養”によってエネルギーを高める行為でもある」と述べています。 つまり、寝るだけでは完全な回復にはならず、意識的に“心・体・社会的環境”の3方向から回復を促す必要があるということです。
この考え方は、筋肥大における「超回復」にも通じます。 筋肉だけでなく、神経・ホルモン・メンタルの全てを休ませることが、トレーニングの成果を最大化する鍵になると言っても過言ではないでしょう。
休養は3分類・7タイプで考えよう
片野秀樹氏は著書『休養学』の中で、「休養とは単に“休むこと”ではなく、“エネルギーを取り戻すための行動”である」と定義しています。 この考え方をベースに、休養を3つの視点から体系化したのが「休養の3分類・7タイプ」です。
人間の疲労は大きく分けて3種類―― 身体の疲れ(生理的疲労)、 心の疲れ(心理的疲労)、 社会的な疲れ(環境ストレス)――から生じます。 それぞれに最適な休養法を当てはめることで、回復のベクトルを“全方位的”に広げることができるのです。
◆ 3つの分類と7つのタイプ
| 分類 | タイプ | 主な方法・例 |
|---|---|---|
| 生理的休養(体の回復) | 休息タイプ | 睡眠・昼寝・安静 |
| 運動タイプ | 軽運動・ストレッチ・ウォーキング | |
| 栄養タイプ | 食事改善・胃腸ケア・内臓休養 | |
| 心理的休養(心の回復) | 親交タイプ | 人との会話・自然との触れ合い |
| 娯楽タイプ | 音楽・映画・読書・ゲーム | |
| 造形・想像タイプ | 瞑想・料理・創作活動・日記 | |
| 社会的休養(環境の回復) | 転換タイプ | 旅行・掃除・模様替え・新しい環境に身を置く |
◆ なぜ7タイプも必要なのか?
たとえば、どんなに睡眠を取っても疲れが取れなかったり、イライラなどのストレスを感じる時がありますよね。 それは、「体」は休めていても「心」や「環境」が休めていないからです。
片野氏は、「人間は多層的に疲れている」と表現しています。 筋トレに例えるなら、筋肉だけでなく神経・ホルモン・メンタルまでが疲労しており、それぞれに対応する“回復のスイッチ”を入れなければ完全には戻らないということです。
そこで、休養では“静と動”のバランスを取る必要があります。 じっと寝ているだけでは「静の回復」に偏り、アクティブレストや交流・創作といった「動の回復」が不足すると気力や集中力が落ちてしまいます。
逆に、動きすぎると今度は体が追いつかなくなる――つまり、休養においては静と動の両面を理解しておくことが大切なのです。
筋肥大を助ける「生理的休養」3タイプの活用法
それではまず、休養の3分類のうちの1つ、「生理的休養」について紹介します。
生理的休養とは、身体そのものの機能を回復させるための休養のことを指します。 筋肉・神経・内臓といったフィジカルな部分に直接アプローチし、疲労を根本から整えていきます。
トレーニーにとって、この生理的休養は「筋肥大の土台」とも言えます。
どれだけハードなトレーニングをしても、睡眠・栄養・回復が追いつかなければ筋肉は成長しません。
つまり、休むこともトレーニングの一部。 ここから紹介する3つのタイプ――「休息タイプ」「運動タイプ」「栄養タイプ」――をバランスよく取り入れることで、トレーニング効果を最大化することが可能です。
①休息タイプ:睡眠と昼寝で筋肉の成長ホルモンを最大化
筋肥大において、睡眠は「栄養」と並ぶ最重要項目です。 ノンレム睡眠の深い段階で分泌される成長ホルモンは、筋繊維の修復と合成を促します。
特に22時〜2時の間は“ゴールデンタイム”と呼ばれ、この時間帯に深く眠ることが理想です。 また、昼寝を15〜30分ほど取ることで、脳の疲労もリセットされ、トレーニングへの集中力が高まります。
ポイント:寝る直前のスマホ使用やカフェイン摂取は睡眠の質を下げるため、就寝1時間前は「ブルーライト断ち」を意識しましょう。
👇睡眠の質を上げる方法については以下の記事でも詳しく紹介していますので、こちらも参考にしてみて下さい。
②運動タイプ:アクティブレストで血流促進と疲労物質の除去
完全休養も悪くありませんが、軽い運動(ウォーキング・ストレッチ・ヨガなど)を行うことで、筋肉に溜まった乳酸や老廃物を除去しやすくなります。 これが「アクティブレスト(積極的休養)」です。
なぜ軽い運動が回復に効くのか?
アクティブレストは「体を少し動かすことで、回復に必要な循環と神経の状態を整える」アプローチです。ポイントは次の通りです。
- 血流が上がる:ふくらはぎや全身の筋収縮が“ポンプ”の役割を果たし、静脈血やリンパの戻りを促進します。これにより酸素・アミノ酸・グルコースが筋肉に届きやすくなり、修復素材の供給がスムーズになります。
- 代謝産物の排出:低強度の反復運動は、代謝で生じた副産物の除去を助け、むくみや重だるさを軽減します。結果としてDOMS(遅発性筋肉痛)が和らぐ効果があります。
- 微小循環と血管機能の改善:ゆるい有酸素で血管内皮にせん断刺激がかかり、一酸化窒素(NO)が出て血管が開きやすい状態になります。これが毛細血管レベルの循環を整え、回復に必要な栄養素を運搬しやすくします。
- 関節液の循環と可動域の維持:ウォーキングやストレッチ等の反復動作は、滑液の循環を促し、こわばりを予防したり、フォームの維持にもプラスに繋がります。
- 自律神経のバランス調整:強度が低い運動+ゆっくりした呼吸は交感神経の過活動をクールダウンし、睡眠や食欲のリズムを整えやすくする効果があります。
ポイント:強度を上げすぎると逆効果になるため、息が少し上がる程度の軽い強度を意識しましょう。
③栄養タイプ:胃腸を休ませる日を作る
胃腸や消化器官の状態が悪いと、せっかく食事やサプリメントから摂取した栄養が効率よく利用されません。
特にトレーニーやボディビルダーは、普段から肉類や卵などを意識して摂取している人も多いでしょう。 ただ、胃腸や消化器官にも“休ませる時間”を設けることで、栄養吸収効率や疲労回復力が上がります。
例えば、普段の鶏胸肉や赤身肉メインの食事を、週に一度は魚中心に変えてみたり、納豆・キムチ・ヨーグルトなどの発酵食品を積極的に摂るのも効果的です。
また、就寝前は消化に良い炭水化物やスープ類を取り入れると内臓に負担をかけません。
このようにして腸内環境が整うと、タンパク質やビタミンの吸収率が上がり、肌や睡眠の質も改善します。
ポイント:「栄養補給」という観点だけでなく、腸内環境を「整える」意識で食事を心がけましょう。
心も回復させる「心理的休養」3タイプの活用法
トレーニングを長く続けていると、「体は元気だけど気持ちが乗らない」「モチベーションが落ちている」という時期があります。 これは身体ではなく“心のエネルギー”が消耗している状態です。 そんな時に必要なのが、心の回復を目的とした心理的休養です。
心理的休養とは、ストレスや緊張で硬くなった心をほぐし、感情のバランスを取り戻すための休養のこと。 片野秀樹氏は『休養学』の中で、「心の疲労は“気づかない疲れ”として蓄積しやすく、身体の回復を遅らせる」と述べています。 つまり、心が休まらなければ、トレーニングの質も上がりにくいということです。
ボディビルや筋トレは、常に“自分との戦い”の連続です。 だからこそ、緊張や競争、完璧主義に偏りすぎると、心が常に戦闘モードになってしまいます。 そんな状態では副交感神経が働かず、回復や睡眠にも悪影響が出てしまいます。
心理的休養では、「人とのつながりを感じる」「トレーニングを純粋に楽しむ」「創作や表現を通して心を整える」といったアプローチで、 心の疲労をリセットし、再びトレーニングに前向きに取り組めるエネルギーを取り戻します。
このあと紹介する3タイプ――親交タイプ・娯楽タイプ・造形タイプ――をうまく使い分けることで、 “メンタルの回復力”が自然と身につき、トレーニングを心から楽しめるようになります。
④親交タイプ:信頼できる仲間が“見えない回復剤”になる
「親交タイプ」とは、〈人や動物、自然との交流を通じて心を休ませる〉休養の形です。
片野秀樹氏は、『休養学』の中で「友人との会話、ペットとの触れ合い、森林浴などは人間のストレスを軽くし、活力を得る“休養の手段”になり得る」と述べています。
つまり、単に「誰かと一緒にいる」ことではなく、“信頼・安心・つながり”を感じられる交流であることがポイントです。 言葉を交わすだけ、近所で軽く会釈をするだけでも、心がほんの少し軽くなり、ストレスの解放につながります。
ポイント:筋トレ中はどうしても自分の世界に入り込みやすいですが、ジム仲間との何気ない会話は「心理的回復」に繋がります。
また、プライベートな時間においても、例えば家族と食事をしたり、ペットと触れ合ったりするなどして「心理的回復」を積極的に行うと良いでしょう。
これらの活動はモチベーションの回復だけではなく、筋肥大の敵である「コルチゾール」の分泌を抑える働きもあります。
⑤娯楽タイプ:好きな時間がメンタルをリセットする
「娯楽タイプ」とは、〈音楽鑑賞・映画・読書・ゲームなど、純粋に“楽しむ”時間を持つ〉ことで心の回復を促す休養の形です。
片野秀樹氏は、「休養とはただ静かに横になるだけではなく、“感情の更新”を伴うことが大切だ」と説明しています。 娯楽には、心の中で“遊び”をし、新しい刺激やリラックスを取り入れる効果があると述べています。
重要なのは、「義務感による行動」ではなく、「自分が心から“やりたい”“楽しい”と思える時間」を意図的に作ることです。 例えば、好きな映画を見る、音楽フェスに出かける、友人とゲームをするなど、日常の“トレーニングモード”からわずかに離れる体験が心をリセットしてくれます。
ポイント:筋トレやボディビルに夢中になると、どうしても「追い込み」「節制」「自己管理」ばかりに気を取られがちです。しかし、そうした“構えっぱなし”の日々では、メンタルが徐々に疲弊します。
そんな時は、映画や音楽、読書など、好きなことに没頭し、脳内にドーパミンやセロトニンを分泌させ幸福度を上げていきましょう。
⑥造形・想像タイプ:内省や創作で自律神経を整える
「造形・想像タイプ」とは、創作や想像を通じて心の回復を促す休養です。
片野秀樹氏は『休養学』の中で、「人間の脳は“創造”しているときにストレスホルモンが下がり、快の神経伝達物質(ドーパミン)が分泌されやすくなる」と述べています。
つまり、創作行為は単なる趣味ではなく、心のバランスを整える生理的な作用を持つのです。
このタイプには、絵画、料理、DIY、プラモデル制作など、“自分の手で何かを形にする”行為が含まれます。 また、創作だけでなく、空想・妄想・回想といった「想像の世界に入る時間」も同じく効果的です。 日常のストレスや思考の枠から一度離れ、“今この瞬間に没頭できる状態”を作ることで、自律神経のバランスが整いやすくなります。
トレーニーにとっても、造形・想像タイプの休養は非常に有効です。
常に結果や数値(挙重量や回数、体重等)ばかりを追っていると、創造的な感覚が薄れがちになってきますが、瞑想、日記、料理、DIYなどの“創る行為”を日常生活に取り入れることで、心を落ち着かせ、自律神経を整えてくれます。
特に大会前のナーバスな時期や減量末期など、メンタルが不安定な時ほど有効です。
ポイント:トレーニング以外の何かに熱中したり、逆に何もしない時間も休養の一つ。頭を空にすることが自律神経を安定させます。
停滞期・マンネリ対策に「社会的休養」1タイプの活用法
社会的休養とは、環境や人間関係など“外の世界との関わり”を通して心身を整える休養法です。
このカテゴリーには「転換タイプ」が含まれ、環境を変えることで心の回復を促すことを目的としています。
⑦転換タイプ:環境を変えることで“心の回復”を促す
「転換タイプ」とは、〈環境や状況を意図的に変えて、心身をリフレッシュさせる〉休養法です。
片野秀樹氏は、『休養学』の中で「同じ景色・同じ行動の繰り返しでは疲れが蓄積しやすい。環境を一時的に変えることが、心身をリセットする契機になる」と述べています。
具体的には、旅行・部屋の模様替え・職場/作業空間の変更など、「いつもと違う体験」を取り入れることで、脳が“次のフェーズ”へ切り替えやすくなります。
「環境の休養」は、身体だけでなく生活リズム・思考パターンまでを整える役割を果たすのです。
筋トレやボディビルにおいても、環境やルーティンが固定化しすぎると“停滞期”や“マンネリ”を招きます。 例えば、
- 休暇を取得して旅行に出かけてみる
- ジムやトレーニングルーティンを変えて新鮮さを取り戻す
- ホームジムがある場合はトレーニングスペースごと模様替えをして気分をリセットする
こうした“環境の変化”が、筋肉・神経・メンタルすべてに良い刺激を入れ、次の成長フェーズに向けた活力を呼び起こしてくれます。
ポイント:気分の切り替えが苦手な人ほど、“環境を入れ替える”工夫をしましょう。
まとめ:休養の捉え方を変えて、筋肥大を最大化させよう
筋肉を成長させるのは「トレーニング」「栄養」「休養」の3要素。 しかし、その“休養”が「睡眠だけ」と思い込んでしまうと、回復の幅を自ら狭めてしまいます。
しかし、本記事で紹介した7タイプの休養を組み合わせて肉体的・精神的・社会的ストレスのすべてをケアできるようになれば、トレーニングの効果をさらに引き上げることができるでしょう。
今日からは「どんな休養を取るか」も日常のルーティンの一部に取り入れてみてはいかがでしょうか?
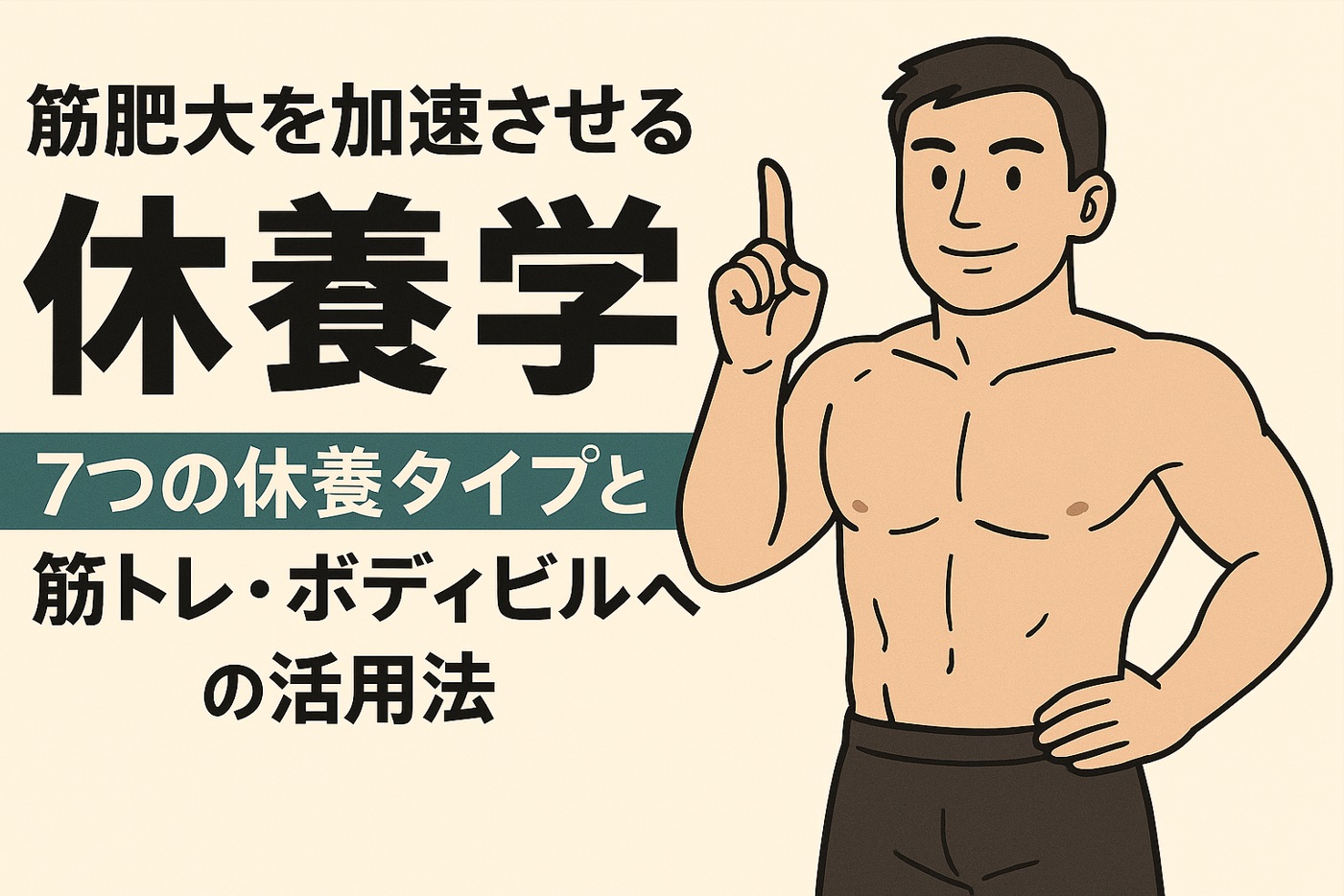


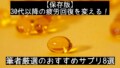
コメント