こんにちは、腹筋がカニの裏の人(プロフィールはこちら)です。
減量後半。
それは、筋トレをしている人にとって最も苦しい時期。
体力は落ち、空腹感に襲われ、そして筋力がガクッと下がっていく──。
…そう思っていた時期が、私にもありました。
でも、今シーズンの減量は違いました。
筋力は落ちなかった。むしろ、種目によっては向上したんです。
これは偶然ではありません。
「コンディショニング」「戦略的トレーニング設計」「回復の見直し」を意識したことで、今年40歳になる自分でも、減量中のトレーニング強度を高く維持することができました。
この記事では、実際に私が行った【減量末期でも強度を落とさなかった7つの工夫】を、実体験ベースで紹介します。
🌟 この記事を読んだらわかること
- ✅ 減量期でもトレーニング強度を落とさないためのコツ
- ✅ 減量期にハイボリュームでやるとどうなる?
- ✅ 減量期に最適なトレーニングボリューム
- ✅ 減量を支えるコンディショニング方法
- ✅ 減量中にやってはいけないNG行動
![]()
味にもこだわりがあり、50種類以上のプロテイン【Myprotein】
種目の優先順位を再設計した
減量後半は「どれだけ疲れを溜めずに、成果の出る刺激を入れられるか」がカギになります。
そこで私は、アイソレート種目などの“効かせる種目”よりも、コンパウンド種目などの“出力を要する種目”を優先しました。
たとえば脚トレ。
以前はレッグエクステンションやレッグカールを多めに入れていましたが、今回はスクワット系やレッグプレス系の種目を中心に構成。
重量を扱う種目を優先することで、神経系への刺激が維持され、強度の「ベース」を落とさずに済みました。
セット数を絞ることで“逆に”強くなった部位がある
意外だったのは、トレーニングボリュームを減らした部位の方が、むしろ強度が上がっていったという事実です。
具体的には以下の部位:
- 脚(前後)
- 臀部(グルート)
- 上腕(二頭・三頭)
- 腹筋
脚や臀部、腹筋に関してはもともと自分の中で強い部位だったこと、そして上腕に関しては、もともと弱い部位ではあったのですが、某トップボディビルダーがセット数を減らして逆に太くなったという意見を参考に、減量に入る前のオフシーズンの頃から、意図的にセット数を落としていました。
脚に関しては、前と後に日を分けてそれぞれ週に12〜15セット、上腕に関しては二頭10セット、三頭12セット、腹筋に至ってはわずか2セットのみ。
にも関わらず、減量中でも挙重量やレップ数が向上していき、先日の大会(東京選手権)を振り返っても、昨シーズンより明らかに筋量が増えていたのです。
ハイボリュームで逆に筋量が落ちた部位もある
一方で、今シーズンの減量ではハイボリュームが裏目に出た部位もありました。
それは以下の3部位:
- 胸
- 背中
- 前腕
これらはもともと自分にとっての弱点部位で、普段から「追い込まなきゃ」という気持ちが強く、減量中もつい高強度+高ボリュームでトレーニングしてしまっていました。
また、「脚(前)→胸→背中→脚(後)→肩→腕」の6分割で回していたのですが、弱点であった胸や背中は肩や腕の日にも1〜2種目を加えていたのです。
結果的に、胸、背中ともに週30セット程度やっていたと思います。
前腕は上腕や背中など様々なトレーニングでも使用する部位ですが、それに加えて前腕に特化したトレーニングも週15セット程行っていました。
しかし結果的に、ボリュームに対しての回復が追いつかず、むしろ筋量が落ちてしまったように感じています。
減量中はアンダーカロリーの状態。
そこに過剰な刺激を加えると、逆に筋肉が削れていってしまう。
この経験は、今後のトレーニング設計にも大きな教訓になりました。
「ボリュームを減らす=サボる」ではなく、「ボリュームを減らす=守る」
この意識がとても大切だと気づかされました。
オーバートレーニングから抜けたからこそ得られた回復と強度
これは先ほどの内容とも関係しますが、今シーズンの自分は、昔よりボリュームを減らしたといっても、いまだにオーバートレーニング気味だったと思います。
- 毎回全力で効かせようとしすぎる
- 弱点部位は週2でトレーニングする
- 「ハリ=効いている」と思い込み、追い込み続ける
それ以来、自分は弱点部位についても意図的にボリュームを落とし、回復を優先した結果、神経系も筋出力も戻ってきたのを実感しました。
中でも特に筋量が落ちてしまった胸については、それ以来「筋肉に張りが戻ってきた」「疲労感なくトレできる」という感覚が戻り、それが今では強度向上と筋肉量維持につながりつつあります。
コンディショニングを最優先にした生活習慣
今年40歳になって痛感するのが、「頑張ることより、整えることがパフォーマンスを作る」という事実。
そのため、今シーズンは以下のような生活習慣を徹底しました:
▶ 睡眠
- 最低8時間を死守
- 起床・就寝時間を固定
▶ 朝の光&軽い散歩
- 体内時計を整え、テストステロンの分泌を促すために毎朝20〜30分のウォーキング
▶ 入浴と筋温管理
- シャワーで済まさず、なるべく入浴をして深部体温を上げて寝つき向上
- 隣駅のゴールドジムに大浴場があったので、有酸素運動ついでにジムまで30分ほど歩き、入浴してまた歩いて帰る日を週に2、3日設ける
- トレ前はしっかりウォームアップして筋温を高める
▶ ストレス管理
- 休日の予定を詰めすぎない
- 自然に触れたり、感覚を取り戻すような“余白時間”を確保
▶ マッサージガンでの首まわりのケア
今シーズン、個人的に非常に効果を感じたのが首〜僧帽筋周辺のリリースです。
トレーニングや仕事で疲労が溜まると、無意識に首が硬直してきます。
特に日々ハードにトレーニングをしているボディビルダーの首には、想像以上に負担がかかっているもの。
しかし、ここは交感神経・副交感神経の切り替えや、中枢神経系の活性と深く関わる部位でもあります。
自分はトレーニング前後や寝る前などに、マッサージガンで首・後頭部・肩甲挙筋あたりを重点的にケアしていました。
すると、
- 睡眠の質が安定
- トレ中の集中力が高まり、筋発揮も向上
- 翌日の回復感も向上
身体がリラックスできることで、副交感神経へのスイッチが入りやすくなり、筋トレ中の発揮力や、睡眠による回復効率にも好影響があったと感じています。
「減量中は交感神経優位になりがち」だからこそ、こうした首まわりのケアが、地味に効いてくるというのは大きな発見でした。
ちなみに、私は首まわりのケアに「MYTREX」というメーカーのマッサージガンを愛用しています。最大の特徴はハンドルが伸縮でき、振動部の角度が調整できること!
| 一般的なマッサージガン | MYTREX | |
|---|---|---|
| ハンドルの長さ | 固定(短い) | 伸縮可能 |
| 振動部の角度 | 固定(まっすぐ) | 自由に調整可能 |
| 届きにくい部位 | 後頭部・肩甲骨は届きにくい | 後頭部・肩甲骨にも直接アプローチ |
👆こちらの比較表のように、MYTREXはハンドルの長さや振動部の角度を調節できるので、後頭部や肩甲骨周りに直接アプローチすることができます。
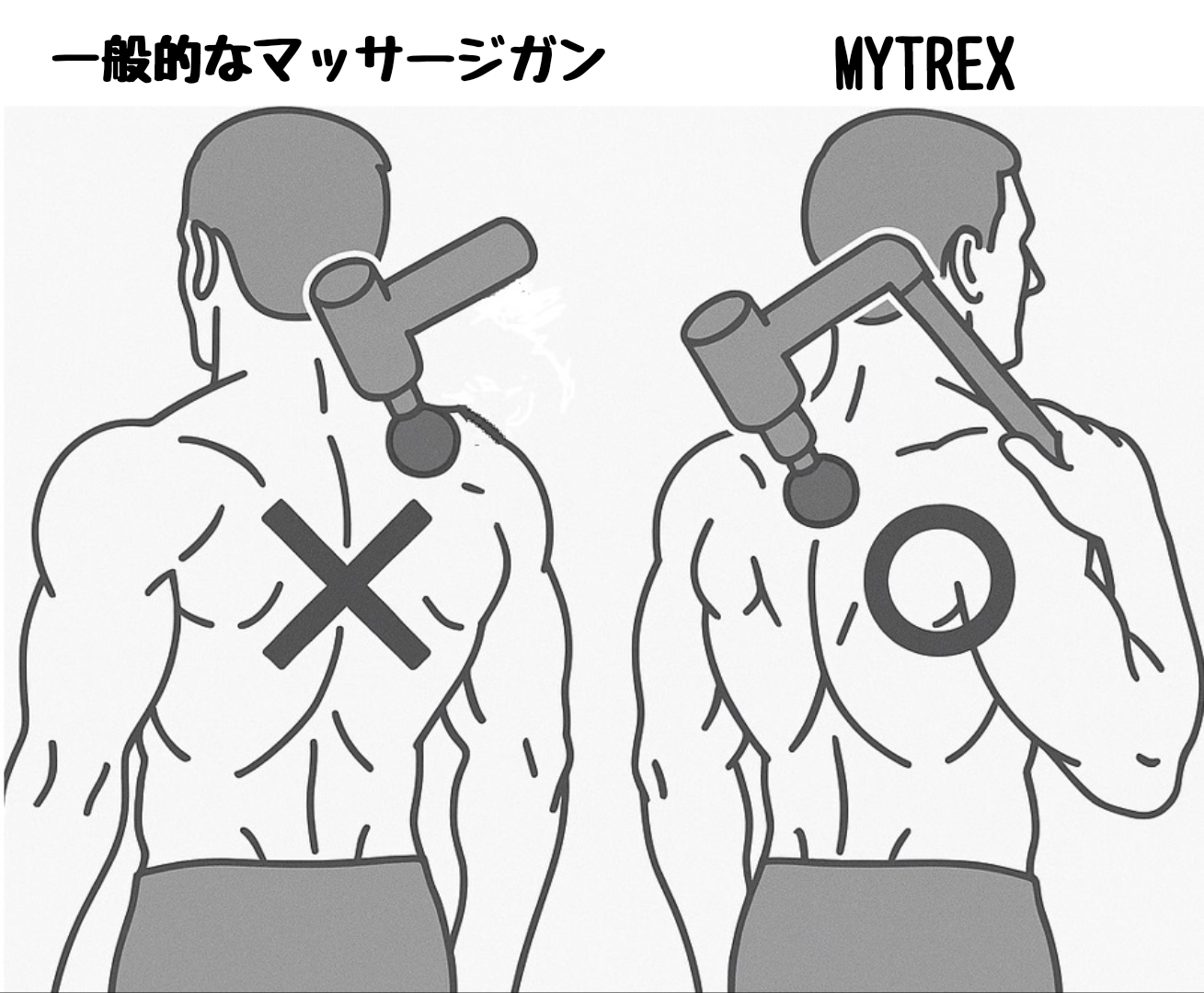
▶筋膜ローラー、コンプレフロスの使用
大腿四頭筋や上腕などに対しては、トレーニング前後に筋膜ローラーやコンプレフロスを使用し、筋膜リリースや関節可動域の改善を行っていました。
これらのコンディショニングによって「トレーニングできる身体」を毎日つくることが、強度を維持する鍵になりました。
動作を“速く”ではなく“丁寧に”行った
重量にこだわりすぎず、1レップの精度・効きに徹底的にこだわりました。
- ネガティブ動作を意識的にゆっくり
- フルストレッチと収縮を確実に
- 反動を使わず、筋肉で上げ切る
減量中の筋肉はナイーブ。
だからこそ、「丁寧な刺激」が筋肉を守ってくれると確信しています。
メンタルの管理と「強くなる減量」の意識
「減量=弱くなる」は思い込みだと、今では感じています。
減量期でも、日々のケアやトレーニングの質を重視することで、筋肉は必ず強化できます。
減量中だからといって言い訳をしない。
そういう、確固たる意志を持つことが大切です。
減量=強くなれない期間ではない。
減量=“自分を整えて、試す”期間でもある。
❌ 減量中にあえて“やらなかった”こと
- HIITや夜サウナなどの交感神経刺激は避けた
- 30分以上続けての有酸素運動
- 毎日トレーニングせず、必ずオフ日を入れた(週に2日)
🏁 まとめ|減量期でも「筋肉を守り、強くなる」
今回の減量で学んだのは、
- 頑張るだけでは強くなれない
- 休ませる勇気こそが筋肉を守る
- 整えることがパフォーマンスの土台
もし今、減量末期に入っているなら、
まずは生活習慣の改善と、トレーニングを“減らす勇気”から始めてみてください。
筋肉は、きっと応えてくれます。
📌 「極限までバリバリに仕上げる方法」についてもこちらで紹介していますので参考にしてみてください!
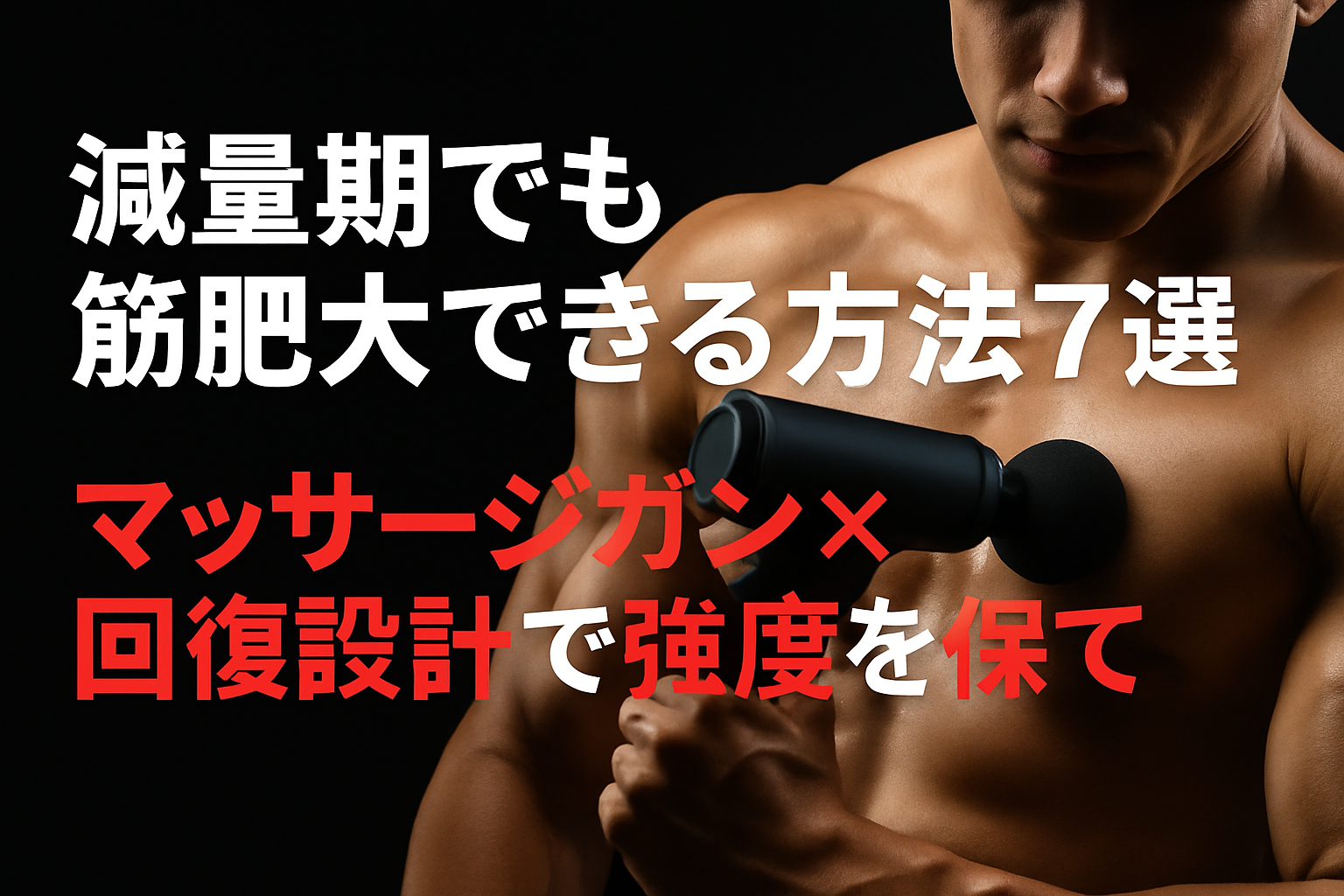


コメント