こんにちは、腹筋がカニの裏の人(プロフィールはこちら)です。
筋トレ界隈ではよく「何時間トレーニングすればいいか?」が交わされることがありますよね。
ボディビルのトップ選手でも、1日1時間程度だったり、2〜3時間と様々。
合戸孝二選手に至っては「4時間×2回 = 8時間」もやっていた時期があるそうです。
これらのトップ選手を見ると時間はあまり関係ないようにも思えますが、果たして実際はどうなのでしょうか?
今回は「筋肥大」に焦点を当てて、果たして何時間がベストなのかを、科学的な根拠と私の今までの経験を元に考察してみたいと思います。
結論:最適な「時間」ではなく、最適な「質×量」を決めること!
いきなり結論ですが、筋トレの最適な時間は「人それぞれ」というのが答えです。
「何時間が正解」ではなく、適切な強度とフォームで必要なボリューム(総セット数)を確保できる時間がベストです。
様々な研究で、週あたりの総セット数が筋肥大の主要因であり、1回あたりの「トレーニング時間」そのものは直接の決定因ではないと示唆されています。
一方で、高強度・長時間の運動はコルチゾールを上げやすいこと、やり過ぎはオーバートレーニングのリスクがあることも知られています。したがって、「必要なボリュームを、無理のない長さで効率良くこなす」という視点が重要です。
科学的視点では「時間」より「中身」
科学的な視点では、以下のようにトレーニングの「時間」よりもその「中身」が重要であることが示唆されています。
ボリューム(総セット数)の重要性
メタ分析を含む研究は、週あたりのセット数(例:10〜20セット/部位)が筋肥大の大きな要因であることが示唆されています。複数日に分割しても、1週間あたりの合算ボリュームが確保できていれば問題ありません。
最適な休憩時間
セット間休憩は2〜3分程度を確保することで、強度を維持しやすく、筋肥大や筋力向上に有利とする研究があります(例:Schoenfeld 2016)。
※最適なインターバルの長さについては以下の記事でも詳しく解説しているので、こちらも参考にしてみてください。
長時間トレーニングの注意点
トレーニング時間が長引くほど、コルチゾール上昇や免疫機能の低下リスクが懸念されます。高強度の長時間化はオーバートレーニングを招きやすいため、「必要なセットを質高くこなしたら切り上げる」という線引きが大切です。
筆者の経験から見えたこと
次に、私のこれまでのトレーニング経験から感じた実体験をもとに、どの程度のトレーニング時間がベストなのかを考察してみたいと思います。
1日5時間のトレーニングをやり込んだ日々(2016〜2020)
私は2016年にボディビルをデビューしてから、1日5時間のトレーニングを5年間続けてきました。
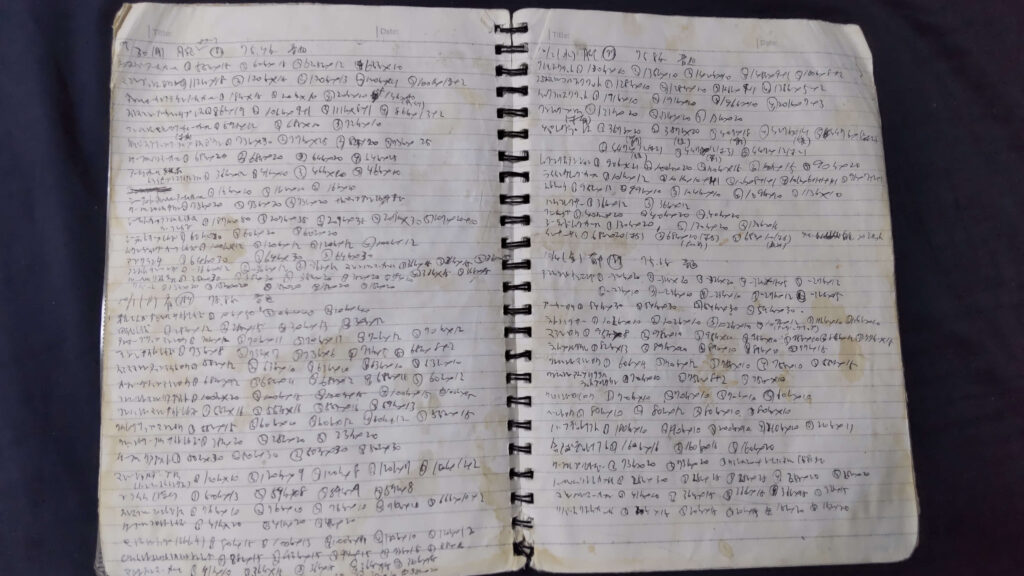
その甲斐あってか、わずかデビュー2年目から以下のようなタイトルを獲得することができました。
【デビュー2年目】
東京クラス別ボディビル選手権70kg以下級優勝
【デビュー3年目】
東京クラス別ボディビル選手権75kg以下級優勝
関東クラス別ボディビル選手権75kg以下級優勝
東日本ボディビル選手権75kg以下級優勝
当時はまだトレーニングフォームはあいまいでしたが、とにかく重量に挑戦し続けていたこと、毎セット限界までやっていたこと、そして毎日ジムの閉館時間までやり続けていたことを今でも覚えています。
そして、大会直前の絞り切った状態の体重は毎年約2kgずつ増えていきました。
- 2016年:68kg
- 2017年:69.8kg
- 2018年:71.4kg
- 2019年:73.4kg
- 2020年:73.8kg(仕上がりは甘め)

誰でも最初のうちは筋肉が成長しやすい傾向はありますが、毎年2kgずつ安定して筋量を増やし続けるのはなかなか難しいものです。
しかも、私がボディビルを始めたのは30歳から。
10代や20代と比べて成長スピードが鈍化していることも考えると、長時間のトレーニングはそれなりに効果はあったように思います。
ボリューム半減と質重視への転換(2021〜)
しかし、年齢も35歳を過ぎてくるとさすがに体力も落ちて、肉体的/精神的に5時間のトレーニングを続けることが困難になってきました。
そこで、2021年からはトレーニング時間を半分程度に減らし、重量ばかりにこだわるトレーニングから脱却。

ここまでトレーニングをやり込んでもこれ以上伸びないのなら、もういいやという、ある意味での開き直りもありました。
当初はボリュームを減らしたり、重量を落とすことで筋量が減るのではないかと不安でしたが、結果的に仕上がり体重は73kg台と変わりませんでした。
しかも、仕上がりは昨年の2020年よりも良く、ジャパンオープン6位、日本クラス別5位と、過去最高の成績を残すことが出来たのです。
この頃には鈴木雅さんのオンラインサロンに入会してアライメントの整え方や、モビリティ・スタビリティを学びトレーニングフォームも安定し始めていたので、その成果が出たようです。
現在(2023年)のトレーニング時間
2022年にオーバートレーニング症候群を発症してからはさらにトレーニング時間を見直し、現在(2023年)はだいたい以下のような感じです。
- 脚の日:3時間15分
- 胸:1時間30分
- 背中:2時間30分
- 肩:2時間
- 腕:2時間
基本的に、トレーニング中の感覚が鈍くなったり、痛みやパンプ感が鈍ったらトレーニングを終えるようにしていますが、しばらく停滞していた記録が最近は少しずつ伸び始め、腕周りが初めて45cmに到達しました。
このことから、時間短縮が必ずしも筋肥大に不利ではないことを実感しています。
過去の経験を通しての考察
私が過去の経験を通して言えるのは、時間と筋肥大には大きな相関はない、と言うことです。
何時間やるかを考える前に、身体のアライメントを整え、正しいトレーニングフォームを身につけることが先決だと考えています。
また、毎セット自分の限界に挑戦し、前回の自分を超える意識を持つことが大切です。

ただ、個人的には長時間のトレーニングもやってよかったと思っています。
なぜなら、
- 呼吸の仕方
- 腹圧のかけ方
- セットに入る前の準備や意識がけ
- 力の入れ方・タイミング・テンポ
- 限界を迎えてから、さらにもう1レップ上げるためのテクニック
など、ボリュームをこなすことでしか得られない細かなテクニックや、「根性」や「忍耐力」といったメンタル面が鍛えられたからです。
まとめ
最後に、長時間トレーニングのメリットとデメリットをまとめておきたいと思います。
メリット
- 多様な種目・角度・テンポを試せるため「自分に合う形」を見つけやすい
- 呼吸・腹圧・力の入れ方・限界からのもう1レップなど、ボリュームをこなすことで得られる微細なスキルが磨かれる
- メンタル面(根性・忍耐力)の強化
デメリット
- 疲労蓄積でフォームが崩れやすい(ケガ・非効率のリスク)
- ホルモン環境や回復に不利になりやすい
- 生活との両立が難しく、継続性が下がる
トレーニングは単純に何時間やればいい、というものではありません。
「もうこれ以上は無理」というのが人によって1時間だったり2時間だったり、あるいは5時間だったりするだけのことだと思います。
ただ、初心者のうちは正しいフォームや体の使い方が良く分からないと思いますので、とにかく高強度のトレーニングを長時間やるのは一つの方法としてアリだと思います。若くて体力のあるうちに量をこなすことにもメリットはあるからです。
ただ、長時間のトレーニングはコルチゾールが分泌されカタボリックになりやすく、オーバートレーニングにも繋がります。
そのため、最終的には、正しいフォームや体の使い方を身に着けた上で高強度のトレーニングを行い、結果的に短時間のトレーニングでオールアウトできた、という形を追求していくことが最適解なのだと思います。




コメント